-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー

TikTokやInstagram、YouTube ShortsなどのSNSを見ていると、
近年ある種の動画が急激に増えていることに気づかれる方も多いのではないでしょうか。
それは、分電盤の中の結線作業を映した投稿 です。
一見すると地味で、一般の方にはあまり馴染みのない作業に思えるかもしれません。
しかし、これらの動画は数万回、時には数十万回も再生され、多くの「いいね」やコメントを集めています。
なぜ今、分電盤の中を見せる投稿 がここまで増えているのでしょうか。
そこには、電気工事という仕事の価値観の変化や、社会の流れが色濃く反映されています。

目次
電気工事の現場において、分電盤はしばしば**「心臓部」**と呼ばれます。
建物全体へ電気を安全に分配し、回路を管理する重要な役割を担っているからです。
分電盤の内部には、数多くの電線が通り、それぞれが正確な位置へと接続されています。
このとき、
配線の曲げ方
余長の取り方
結線の順序
全体構成
といった要素のすべてに、施工者の技量や経験、思考の深さが表れます。
業界では昔から、
「分電盤を見れば、その人の仕事のレベルがわかる」
と言われてきました。
つまり分電盤の結線は、電気工事士にとっての“腕の見せ所” とされてきたのです。
これまでは、こうした仕上がりを見ることができるのは、同業者や検査担当者に限られていました。
しかしSNSの普及により、分電盤の中の様子が誰の目にも触れる時代になりました。
この変化が、投稿増加の大きな背景のひとつになっています。
分電盤の中を美しく仕上げることは、単なる見た目の問題ではありません。
そこには、安全性・合理性・将来性といった、実務上の明確な理由があります。
配線が乱雑な状態では、
締結部の緩み
電線の摩耗
熱のこもり
被覆の損傷
などが起こりやすくなります。
整然と整理された結線は、こうしたリスクを大きく軽減し、
長期間にわたって安全に使用できる環境をつくります。
分電盤は、設置して終わりではありません。
点検や改修、設備の追加などで、将来的に何度も開けられることになります。
配線が整理されていれば、
どの回路がどこにつながっているのか
どこを触ればよいのか
が一目で分かり、作業時間の短縮と事故防止につながります。
分電盤の中は、施工品質をそのまま映し出す鏡のような存在です。
配線が美しく整っている盤内を見ると、
「丁寧な施工が行われている現場である」という印象を自然に与えます。
つまり、美しさとは施工品質の結果として現れるもの と言えるのです。
これまで、分電盤の中は完成後にフタを閉じられ、
施主が目にすることはほとんどありませんでした。
どれほど丁寧な作業が行われていても、その価値が伝わる機会は限られていたのです。
しかしSNSの登場によって、この状況は大きく変わりました。
タイムラプス動画
ASMR形式の作業音
ビフォーアフターの比較
こうした表現方法を通して、職人が大切にしてきた美意識や仕事観が、
誰にでも分かる形で共有されるようになりました。
その結果、分電盤の結線作業は、
ただの裏方作業
→ 見て楽しめるコンテンツ
へと変化していったのです。
分電盤の結線動画が多くの人を惹きつける理由は、
人間の視覚と心理の特性にも関係しています。
直線
直角
規則的な並び
整然とした構成
これらは、脳が心地よさや安心感を覚える要素だとされています。
乱雑な状態から整った状態へと変化していく過程は、
掃除や整理整頓の動画と同様に、「整う快感」を強く刺激します。
分電盤の結線作業は、
高度な技術 × 規則美 × 変化
が同時に成立する、非常に相性の良い題材なのです。
分電盤の中を積極的に見せる動きは、
電気工事という仕事の捉え方が変化しつつあることも示しています。
かつての職人像は、
体力勝負
根性論
長時間労働
といったイメージと結びつきがちでした。
しかし現在のSNSでは、
段取り
思考
設計
美意識
といった知的側面が強く表現されています。
分電盤の結線は、この変化を象徴する存在だと言えるでしょう。
配線の一本一本に込められた工夫や配慮が可視化されることで、
職人という仕事の価値そのものが、あらためて見直され始めています。
分電盤の中を美しく仕上げるという行為の本質は、
単なるテクニックではありません。
見えなくなる部分こそ丁寧に仕上げる
誰も見ていなくても手を抜かない
次に触る人のことまで考える
こうした仕事に対する姿勢や価値観が、
配線の一本一本に表れています。
だからこそ、人は分電盤の中に惹かれるのかもしれません。
そこに映っているのは、
電線の並び以上に、働き方そのものの美しさなのではないでしょうか。
目次
「電気工事の仕事は、危険で大変そう」
多くの方が、こうしたイメージを持っています。
高所作業
足場の上での作業
電柱に登る仕事
夜間工事や長時間労働
確かに、電気工事の世界には、そうした現場が数多く存在します。
しかし実は、電気工事という仕事の安全性や働きやすさは、「どんな現場を選ぶか」で大きく変わるのです。
コイデンは創業以来、
**「安心して働ける現場環境をつくる」**ことを軸に、
あえて“現場の選び方”に強くこだわってきました。

厚生労働省の労働災害統計によると、
建設業における死亡事故の**約4割が「墜落・転落」**です。
電気工事業に限って見ても、
感電事故よりも高所作業中の転落事故の方が圧倒的に多いことが分かっています。
つまり、電気工事における最大のリスクは、
高い場所で作業することそのもの
だと言えます。
コイデンの主な施工領域は、
マンションリフォーム
住戸内電気工事
中規模店舗・クリニック
です。
これらの現場では、
天井高:おおよそ2.4〜2.7m
仮設足場:ほぼ不要
高所作業車:使用なし
電柱作業:ほぼ無し
という特徴があります。
結果として、
転落事故の最大要因となる「高所作業」そのものが、日常業務からほぼ消えています。
これは、安全管理の工夫以前に、
仕事の選び方=業務設計の段階で、リスクを下げているという考え方です。
もう一つ、働きやすさに直結するのが夜間工事の有無です。
ビルや商業施設、工場などの現場では、
営業終了後
生産停止後
交通量が少ない深夜帯
に工事を行うケースが多く、
夜間作業が常態化しやすくなります。
一方、マンションリフォームや中規模店舗工事では、
日中作業が基本
17時前後で作業終了
深夜工事は原則なし
という働き方が可能です。
生活リズムが安定することは、長く健康的に働くうえで非常に重要です。
多くの電気工事会社は、
危険な作業を、どう安全に行うか
という方向で安全対策を考えます。
もちろんそれも重要です。
しかし、コイデンが大切にしているのは、
それ以前の発想です。
危険な作業を減らす仕事の設計をする。
これにより、
事故リスクの低減
身体的負担の軽減
精神的ストレスの減少
長期就業の実現
が同時に成立します。
電気工事の仕事は、技術職であり、職人仕事です。
だからこそ、
体を壊さないこと
無理な働き方をしないこと
家庭と両立できること
が、長期的に非常に重要になります。
コイデンでは、
高所作業が極端に少ない
夜間工事がほぼ無い
残業がほとんど無い
日曜・祝日・長期休暇が明確
という環境を整え、
**「10年、20年と働ける職場」**を目指しています。
高所作業が怖い、または不安な方
夜勤や不規則な生活から抜け出したい方
家族との時間を大切にしたい方
安定した環境で、じっくり技術を身につけたい方
電気工事の仕事は、
「どの現場を選ぶか」で、人生の質が大きく変わります。
電気工事は、確かに専門性が高く、責任も大きい仕事です。
しかし、
高所作業なし
夜間工事なし
無理な工程なし
という環境を選ぶことで、
安全性も、働きやすさも、大きく変わります。
コイデンは、
**「安心して働ける現場設計」**を軸に、
これからの電気工事の新しい働き方を提案し続けます。
コイデンでは、
マンションリフォーム・中規模店舗工事を中心に、
一緒に長く働ける仲間を募集しています。
▶ 募集要項・お問い合わせはこちら
電気工事士として経験を積んでくると、
こんな不安を感じることはありませんか?
年数は重ねてきたが、立場は変わらない
現場は回せるが、裁量は増えない
この先、どんなキャリアがあるのか見えない
この不安は、
「独立できるかどうか」だけが原因ではありません。
本当の不安は、
経験を積んでも“次の役割”が用意されていないことです。
この記事では、
東京都練馬区を拠点に電気工事を行う
**株式会社コイデン**が、
なぜすぐに管理を任せないのか
どんな人材を、どんなルートで育てたいのか
その考え方をお伝えします。
目次
コイデンでは、
入社してすぐに「現場管理」や「代理人業務」を
任せることはしていません。
理由はシンプルです。
管理の仕事は、技術だけでは務まらないから。
現場での立ち振る舞い
他業種・元請・施主との関係性
トラブル時の判断
言葉の選び方
これらは、
図面や資格だけでは測れません。
だからコイデンでは、
まず社員として現場をじっくり経験してもらう。
その中で、
技術力
仕事への姿勢
人としての信頼感
を見たうえで、
「任せられる」と判断して初めて、
次の役割を渡します。
コイデンの仕事は、
マンションリフォームが中心です。
しかし今、会社として力を入れているのが、
中規模店舗
クリニック
テナント工事
といった、
工程・調整・責任が一段上の現場です。
これらの現場では、
ただ施工ができる
指示を待って動く
だけでは通用しません。
現場全体を見渡す力
相手の立場を理解する力
問題を未然に防ぐ判断
そういった力を持つ人材が必要になります。
コイデンでは、
電気工事士のキャリアを
「独立するか、しないか」
の二択で考えていません。
職人として、現場を正確にこなせる
現場全体を見て動ける
管理・調整を任される
社内の中核として現場を任される
このステップを踏むことで、
現場代理人
管理を担う技術者
社内のリーダー
といった立場へ進んでいきます。
そして重要なのは、
役割が上がれば、サラリーも上げる準備がある
という点です。
責任だけを増やすことはしません。
電気工事業界では、
「数年で独立」という言葉が
簡単に使われがちです。
しかし現実には、
経験年数と事業の安定は別
顧客は簡単には作れない
元請依存になり、価格を叩かれる
体力と資金だけが削られる
そういったケースを、
コイデンは何度も見てきました。
だからこそ、
独立をゴールとして煽ることはしません。
まずは、
社内で信頼され
現場を任され
安定した立場と収入を得る
その上で、
自分の将来を選べる状態になること。
それが、
人にとっても、業界にとっても
健全だと考えています。
現場作業だけで終わりたくない
技術だけでなく、人間性も評価されたい
管理や調整を任される存在になりたい
腰を据えて、価値を積み上げたい
コイデンは、
「早く結果を出したい人」よりも、
**「任せられる人になりたい人」**を歓迎します。
電気工事士の将来は、
独立するかどうかで決まるものではありません。
どんな現場を経験するか
どんな会社で、どんな役割を任されるか
それによって、
5年後、10年後の立場は大きく変わります。
コイデンは、
人を急がせません。
その代わり、
任せると決めたら、きちんと評価します。
将来に少しでも迷いがあるなら、
一度、コイデンの考え方を知ってください。

「電気工事士の仕事は、正直きつい」
残業が多い
予定が読めない
家に帰るのが遅い
そんなイメージを持っている方も多いと思います。
実際、業界全体を見れば、それは間違いではありません。
ただし――
すべての電気工事会社が同じ働き方をしているわけではありません。
この記事では、
**株式会社コイデン**が
なぜ「残業ほぼゼロ」という働き方を実現できているのか、
その理由を正直にお話しします。

目次
まず前提として、
電気工事士の仕事がきつくなりやすい理由は、人の問題ではありません。
多くは、次のような構造的な理由です。
突発工事・夜間対応が多い
工程が詰め込まれすぎている
現場が日替わりで変わる
人手不足を気合でカバーしている
この状態では、
どんなに真面目な職人でも疲弊してしまいます。
コイデンでは、創業当初から
あえてやらないことをはっきり決めています。
マンションリフォーム専門のため、
工事時間は 9:00〜17:00 が基本。
「急だから今日来てほしい」
「夜しか空いていない」
といった案件は、基本的に受けません。
1日に詰め込む現場数を制限し、
必ず17:00に撤退できる工程を前提に組みます。
結果として、
残業はほぼなし
多くても月数時間程度
という状態を維持しています。
「残業しない」と言うのは簡単ですが、
それを実現するには仕組みが必要です。
コイデンでは、
事前の現地調査を丁寧に行う
材料・段取りを前日までに確定
当日の判断を減らす
といった、準備に時間を使う働き方をしています。
現場でバタバタしない分、
精神的な負担もかなり少なくなります。
誤解してほしくないのは、
コイデンの仕事が「楽」なわけではありません。
技術はきちんと求められる
施工の丁寧さも重視される
お客様との信頼関係も大切
ただしそれは、
無理を強いられるきつさではなく、
職人としての健全な緊張感です。
子どもの行事に参加したい
平日の夜も自分の時間がほしい
体を壊さず、長く働きたい
そう考える電気工事士にとって、
働き方はとても重要です。
コイデンでは、
「仕事のために生活を犠牲にする」
という考え方はしていません。
電気工事士の仕事は好き
でも、今の働き方には疑問がある
落ち着いた環境で技術を活かしたい
無理なく、長く続けたい
もし一つでも当てはまるなら、
コイデンの働き方は合うかもしれません。
電気工事士の仕事は、
本来「きついだけの仕事」ではありません。
どんな現場を選び、
どんな会社で働くか。
それだけで、
仕事の続けやすさは大きく変わります。
少しでも気になった方は、
まずは話を聞くだけでも構いません。
お気軽にお問い合わせください。
「電気工事士の仕事は好きだけど、
残業や無理な現場が当たり前なのは正直つらい」
「家族や自分の時間を大事にしながら、
ちゃんと技術を活かして働きたい」
そんなふうに感じて、求人を探している方も多いのではないでしょうか。
この記事では、東京都練馬区でマンションリフォームを中心に電気工事を行っている
株式会社コイデンの働き方を、良いことも・向き不向きも含めて正直にお伝えします。

目次
電気工事士の求人を見ると、
「未経験OK」
「高収入」
「アットホームな職場」
といった言葉が並びがちですが、
実際に働き続けられるかどうかは、次の点で大きく変わります。
どんな現場がメインか
勤務時間がどれくらい守られているか
無理な詰め込みがないか
人間関係や社内の雰囲気
コイデンは、この中でも特に
**「現場の質」と「働く時間」**を大切にしている会社です。
コイデンは、東京都練馬区を拠点に
マンションリフォームを中心とした電気工事を行っています。
新築現場や突発対応がメインではなく、
分電盤交換
配線のやり替え
照明・コンセント工事
LED器具交換
といった、計画的に進められる工事がほとんどです。
そのため、
「今日は何時に終わるかわからない」
「急に夜間対応が入る」
といったことは、ほぼありません。
コイデンの基本的な勤務時間は以下の通りです。
9:00 現場作業開始
16:45 片付け開始
17:00 完全撤退
マンションリフォーム中心のため、
工事時間が9:00〜17:00に限定されています。
その結果、
残業はほぼなし
一番多い社員でも月4時間程度
残業手当は全額支給
「電気工事=長時間労働」というイメージとは、
少し違う働き方ができる環境です。
休日もしっかり確保しています。
日曜・祝日
年末年始
家族行事や私用についても、
会社全体でフォローする文化があります。
「休むと肩身が狭い」
そんな雰囲気はありません。
コイデンは、次のような方に向いています。
第二種電気工事士の資格を活かしたい
無理な働き方をせず、長く続けたい
現場だけでなく、段取りや信頼関係も大事にしたい
逆に、
とにかく短期間で稼ぎたい
夜間・突発工事もバンバンやりたい
という方には、合わないかもしれません。
Q. ブランクがあっても大丈夫?
A. 問題ありません。経験や状況に応じて、無理のない形で現場に入ってもらいます。
Q. 年齢制限はありますか?
A. 特にありませんが、ご経験の内容やお人柄を重視していますので、30〜40代とさせていただいてます。
Q. 独立を目指していても応募できますか?
A. もちろんです。5年で独立を視野に入れる方もいます。
電気工事士の仕事は、
**「誰と、どんな環境でやるか」**で、
続けやすさも人生も大きく変わります。
コイデンは、
派手さはありませんが、
誠実に、現実的に、長く働ける会社です。
少しでも気になった方は、
まずはお気軽にお問い合わせください。
2025年も残りわずかとなりました。
平素より、株式会社KOI-DENのブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。
今年は、ブログを通じて多くの方に
電気工事や住まいの電気に関する情報をお届けしてきました。
「ブレーカーがよく落ちる」
「電気容量が足りているのか不安」
「分電盤って交換時期があるの?」
そんな日々の小さな疑問から、
実際のご相談・ご依頼につながる機会も少しずつ増え、
“小さいけれど、未来につながるステップ”を積み重ねられた一年だったと感じています。
2025年は、
むやみに業務を広げるのではなく、
ブログ読者の方からのご相談対応
スケジュール管理や業務連絡の最適化
現場と事務の連携をスムーズにする仕組みづくり
といった、足元を整える取り組みに力を入れてきました。
大きな変化ではありませんが、
ひとつひとつの改善が、
「無理のない対応」「丁寧な工事」「安心できるご提案」
につながっていると考えています。
私たちは、
「とりあえず工事をする」よりも、
今の暮らしに本当に必要かどうかを一緒に考えることを大切にしています。
ブログも同じです。
すぐに工事につながらなくても、
「知っておいてよかった」
「判断の材料になった」
そう思っていただける情報を、これからも発信していきます。
誠に勝手ながら、下記期間を年末年始休業とさせていただきます。
年末年始休業期間
📅 2025年12月27日(金)〜 2026年1月4日(土)
休業期間中にいただいた
お問い合わせ・ご相談につきましては、
1月5日(日)以降、順次対応いたします。
ご不便をおかけいたしますが、
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
2026年も、
住まいの電気を通して、
安心して暮らせる毎日を支えられるよう、
一つひとつの仕事に丁寧に向き合ってまいります。
どうぞ良いお年をお迎えください。
こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社コイデン」です。
年末年始、こんな経験はありませんか?
親や兄弟が集まった途端にブレーカーが落ちた
料理中に電子レンジを使ったら真っ暗になった
普段は問題ないのに、この時期だけ電気が不安定
実はこれ、
年末年始に電気トラブルが急増する典型パターンです。
この記事では、
なぜ年末年始に電気トラブルが起きやすいのか
家族が集まる家ほど注意すべきポイント
事前にできる対策と工事の判断基準を、
電気工事の視点からわかりやすく解説します。

目次
理由はシンプルで、
「一気に電気を使う条件」が重なりすぎるからです。
家族・親戚が集まる
在宅時間が長くなる
料理・暖房・娯楽家電が同時稼働
普段使わない家電も登場
👉 普段は分散していた電気使用が、
短時間に集中するのが年末年始です。
例えばこんな同時使用、心当たりありませんか?
リビング:エアコン+こたつ+テレビ
キッチン:電子レンジ+炊飯器+IH
洗面所:ドライヤー+暖房
充電:スマホ・タブレット・ゲーム機
これだけで、
一般的な家庭の電気容量は簡単に限界を迎えます。
最も多いのがこれ。
家全体が停電する
夜や料理中に起きやすい
何度も繰り返す
原因の多くは、
契約アンペア不足 or 電気容量オーバーです。
キッチンだけ使えない
リビングのコンセントが落ちる
これは、
回路の分け方が昔のままな家でよく起きます。
👉 特定の場所に家電が集中すると、
部分的にブレーカーが落ちます。
年末年始は、
延長コード
タコ足配線
仮設的な家電配置
が増えがち。
コンセントが熱くなる
焦げ臭い
コードが異常に暖かい
👉 これは火災リスクにつながる危険サインです。
普段問題がない家ほど、
年末年始の負荷に耐えられないケースがあります。
「今まで落ちたことがない」
「古い家じゃないから平気」
「年に一度だけだから我慢」
👉 でも実際は、
一番電気を使う日が年末年始。
このタイミングで起きるトラブルは、
家の電気環境の限界が見えているサインです。
検針票・電力会社マイページで確認
家族が集まるなら40A以上が目安
空き回路はあるか
古くて文字が読めないブレーカーはないか
よく落ちる回路が決まっていないか
熱・変色・焦げ跡
グラつき
延長コードの多用
👉 1つでも当てはまれば要注意。
次のような場合は、
年明けを待たずに相談する価値ありです。
年末年始に何度もブレーカーが落ちた
家族が集まると必ず電気が不安定
分電盤が20年以上前
将来リフォームやEV導入予定
契約アンペア変更
分電盤交換
回路増設・専用回路新設
👉 「年に1回の問題」ではなく、
これからの生活を楽にする工事になります。
電気トラブルは、
起きてからでは遅い
夜・休日ほど困る
家族が集まるほどストレスが大きい
だからこそ、
何も起きていない今の点検が一番安全で安価です。
年末年始は電気使用が集中する
家族が集まる家ほどトラブルが起きやすい
ブレーカーが落ちるのは家からの警告
「今年は大丈夫だった」ではなく、
「これからも安心して使えるか」。
それを考えるきっかけが、
年末年始の電気トラブルです。
こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社コイデン」です。
冬になると、こんなことを感じたことはありませんか?
「暖房つけただけで電気代が一気に上がった」
「去年より請求額が高い気がする」
「節約してるのに、なぜか下がらない」
実はこれ、
使い方の問題だけではなく、家の電気環境そのものが原因になっているケースが少なくありません。
この記事では、
冬に電気代が急上昇する本当の理由と
**見落とされがちな「電気容量の落とし穴」**を、
電気工事の視点からわかりやすく解説します。

目次
まず前提として、冬は他の季節と比べて
圧倒的に電気使用量が増えます。
エアコン(暖房)
電気ストーブ・セラミックヒーター
こたつ
加湿器
電子レンジ・炊飯器
浴室乾燥機
これらはどれも
消費電力が高い or 長時間使う家電です。
👉 夏は「エアコンだけ」でも、
冬は「暖房+生活家電」が重なりやすいのが特徴です。
エアコン暖房は、
スイッチを入れた直後に一気に電力を使います。
部屋を温めるまでフルパワー
外気温が低いほど負荷が大きい
つまり、
寒い朝・帰宅直後・夜は
電気使用量がピークになりやすい時間帯です。
築年数が経っている住宅では、
30A
40A
のまま使われていることも珍しくありません。
しかし現在は、
エアコン
電子レンジ
IH
浴室乾燥機
など、同時使用が前提の生活。
👉 容量が足りないと、
ブレーカーが落ちる
無意識に使うのを我慢する
それでも電気代は下がらない
という、ストレスだけが溜まる状態になります。
意外と知られていませんが、
電気代と分電盤の構成は無関係ではありません。
リビングの暖房とコンセントが同じ回路
キッチン家電が1回路に集中
回路数が少ない
こうなると、
一部に負荷が集中
無駄にブレーカーが落ちる
効率が悪くなる
👉 電気を「使っている量」以上に、
使い方が悪くなっているケースも多いです。
「こまめに消してるのに…」
「設定温度も低めなのに…」
それでも電気代が下がらない場合、
家の電気設計が今の生活に合っていない可能性があります。
電気容量がギリギリ
家電を我慢しながら使用
結果、暖房効率が悪い
👉 実はこれ、
必要以上に電気を消費している状態です。
検針票や電力会社のマイページで確認できます。
3人以上家族 → 40A以上が目安
オール電化・IHあり → 50〜60A検討
空き回路はあるか
同じ場所に負荷が集中していないか
築20年以上なら、
一度プロに見てもらう価値ありです。
朝の暖房使用時
夕方〜夜の家事時間
この時間帯に落ちるなら、
冬特有の電気容量不足のサインです。
契約アンペアの変更
分電盤の交換
回路の増設・分離
専用回路の新設
これにより、
ブレーカーが落ちにくくなる
暖房効率が安定
無駄な電力消費を防げる
👉 結果的に
電気代が安定しやすくなるケースも多いです。
寒さを我慢したり、
家電の同時使用を避け続けるのは、
長い目で見るとストレスも危険も増えます。
家族が安心して暖房を使える
電気トラブルの不安が減る
将来のリフォームにも対応しやすい
これが、
電気環境を整える一番のメリットです。
冬は電気を使う量が一気に増える
暖房+生活家電で負荷が集中
電気代が高い=使いすぎとは限らない
「毎年冬になると電気代が高い」
それは、
家からの見直しサインかもしれません。
こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社コイデン」です。
年末が近づくと、こんな声が増えてきます。
「掃除機を使ったらブレーカーが落ちた」
「暖房をつけたまま電子レンジを使ったら真っ暗に…」
「大掃除の途中で家中の電気が止まった」
実はこれ、年末あるあるの電気トラブルです。
しかも原因は「古い家だから」だけではありません。
この記事では、
年末の大掃除前に必ずチェックしておきたいブレーカーが落ちる原因と、
自分でできる確認ポイント・工事が必要な判断基準まで、わかりやすく解説します。

目次
年末は、1年の中でも電気を一気に使う時期です。
掃除機を長時間使う
電気ストーブやエアコンをつけっぱなし
電子レンジ・オーブン・炊飯器の使用頻度増加
こたつ・加湿器・乾燥機の稼働
これらが同時に動くことで、
家全体の電気使用量が一気に上がります。
👉 その結果、
契約アンペアや分電盤の容量を超えてブレーカーが落ちる、というわけです。
昔の住宅では、
30A
40A
といった低めの契約アンペアのまま使われているケースが少なくありません。
しかし現在は、
エアコン
IH
電子レンジ
食洗機
など、同時使用が前提の家電が増えています。
👉 家族構成や生活スタイルが変わっているのに、
電気の契約だけ昔のままというのは、かなり危険です。
分電盤には「家全体の電気の通り道」が集まっています。
回路数が少ない
空きがない
経年劣化している
こうした状態だと、
一部の回路に負荷が集中しやすく、ブレーカーが頻繁に落ちます。
特に築20年以上の住宅では、
分電盤そのものが現在の電気使用に対応していないことも多いです。
年末の大掃除では、こんな使い方をしがちです。
延長コードでタコ足配線
同じコンセントに掃除機+暖房
キッチン家電を同時使用
これも、
ブレーカーが落ちる大きな原因。
実は「電気容量は足りているのに、使い方で落ちている」ケースも少なくありません。
「主幹ブレーカー」のアンペア数
ブレーカーに「落ちた跡」が多くないか
古くて文字が読めないブレーカーがないか
👉 これだけでも、危険サインが見えることがあります。
掃除機+暖房
電子レンジ+エアコン
この時、
電気が一瞬暗くなる
ブレーカーが落ちそうな音がする
なら、容量ギリギリの可能性大です。
熱を持っていないか
焦げ臭くないか
グラつきがないか
👉 異常があれば、すぐ使用をやめてください。
年末だけ一時的に落ちる
使い方を変えたら改善する
家電の同時使用を減らせば問題ない
何度もブレーカーが落ちる
家族が増えた/在宅時間が長くなった
EVコンセントやIHを使っている
分電盤が20年以上前
👉 この場合、
契約アンペアの変更や
分電盤の交換・回路増設で根本解決できます。
年末年始を安心して過ごせる
家族が集まっても電気トラブルが起きにくい
電気火災のリスクを下げられる
将来のリフォームやEV導入にも対応しやすい
「何も起きていない今」が、
実は一番安く・安全に対処できるタイミングです。
年末の大掃除は、
家の中をきれいにするだけでなく、
電気の使い方・安全性を見直す絶好の機会です。
ブレーカーが落ちるのは、家からのSOS
我慢で乗り切るより、原因を知る方が安全
小さな点検が、大きなトラブルを防ぐ
「これって大丈夫かな?」
そう感じたら、早めに専門家に相談してみてください。
こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社コイデン」です。
目次
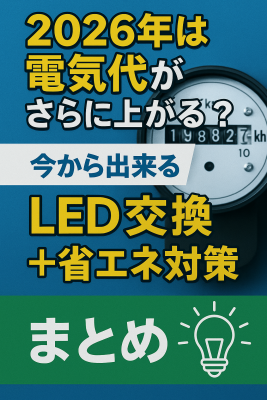
2025〜2026年にかけて、日本では電気料金の値上げ圧力が続くと予測されています。
その背景には…
燃料価格(LNG・石炭)の高騰
老朽化した発電設備の更新費用
再エネ拡大に伴う送電網整備費
円安による輸入コストアップ
こうした要因が重なり、2026年は「電気代の見直し」が本格化する年と言われています。
マンションやクリニック、店舗を運営するオーナー様にとっては、
“省エネ対策を前倒しする”ことがコスト削減の最重要ポイントになります。
電気代を安くする施策の中でも、
コスト削減効果が高いのは圧倒的に“LED照明への交換”です。
蛍光灯からの交換で 40〜60%の省エネ
球切れがほぼなく、交換頻度が減る
点灯安定性が高く、冬でもチラつきにくい
放熱が少なく安全性が高い
特にマンション共用部では、
24時間点灯の照明が多いため、効果はさらに大きくなります。
廊下・階段・トイレ・物置・駐輪場などに最適。
メリット:
不要な点灯を削減
夜間の安全性が向上
住民からの満足度も上がる
共用トイレやバックヤードにおすすめ。
つけっぱなし防止
24時間換気のしすぎによる電気代を削減
冬の湿気・結露対策にも有効
古い建物では、1つの回路に複数の機器がぶら下がっているケースが多数。
過負荷の原因
ブレーカー落ち
配線の劣化 → 修繕費が高額化
省エネ以前に“安全性”の観点でも見直しが必要です。
照明器具の数・種類・高さによって大きく変わりますが、
蛍光灯型:1台あたり約8,000〜20,000円
器具丸ごと交換:1台あたり約15,000〜40,000円
が一般的な目安です。
標準的なマンションなら…
10〜30台:半日〜1日
50台以上:1〜2日
住民の生活に支障が出ないように施工可能です。
電気工事は複数箇所まとめて依頼すると、
移動・段取りコストが1回で済むため、費用が抑えられます。
LED交換
スイッチ・コンセント交換
浴室換気扇の更新
エアコン入替
などをセットで行うと最もお得です。
マンションリフォーム中心のコイデンでは、
共用灯のLED化工事
人感センサー照明の導入
店舗・クリニックの照明計画
電気代削減のアドバイス
退去リフォームの同時施工
といった、省エネニーズの高い12〜3月の案件に特に対応しています。
2026年の電気代上昇に備えるなら、
「今年の年末〜年度内」に対策するのが最も効率的です。
2026年の電気代は、これまで以上に上昇する可能性があります。
その中で最も費用対効果が高いのが、
LED交換
人感センサー・タイマー導入
回路の見直し
今から準備しておけば、来年のコストを大きく抑えることができます。
省エネ対策を始めるなら、
“今日がいちばん早い日” です。