-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー

はじめに
こんにちは。練馬区桜台で一番勢いのある電気工事会社「株式会社KOI-DEN」です。
洗濯物を乾かすのに 「浴室乾燥機」 を使っていますか?
浴室乾燥機は、雨の日や冬場に洗濯物を部屋干しする家庭にとって、とても便利なアイテム です。
「でも、電気代が高そうだし、あまり使っていない…」という方もいるのでは?
実は、浴室乾燥機は 洗濯物を乾かす以外にも、意外な便利な使い方 があるんです!
この記事では、 浴室乾燥機の隠れた活用法 を紹介するとともに、 知っておきたいデメリット についても解説します。
まず、浴室乾燥機には 3つの基本機能 があります。
機能 主な用途
乾燥機能 洗濯物を乾かす、浴室を乾燥させる
暖房機能 冬場の浴室を暖める
換気機能 湿気を外に排出し、カビ防止
最近の浴室乾燥機は、これらに加えて 冷風機能(涼風) なども搭載されており、 1年中使える便利な設備 なんです!
① 洗濯物の乾燥時間を短縮するコツ
浴室乾燥機は便利ですが、「なかなか乾かない…」「電気代が気になる…」という声もあります。
そこで、 乾燥時間を短縮するコツ を紹介します!
✅ 乾燥効率を上げるポイント
1. 洗濯物の間隔を空ける → 風の通り道を作る
2. ハンガーを前後にズラして掛ける → 風がまんべんなく当たる
3. バスタオルなどの厚手のものは端に干す → 乾きにくいものは風の当たりやすい場所に
4. 送風機やサーキュレーターを併用する → 空気を循環させて乾燥を促進
タオルがパリパリになってしまうのが嫌な人へ!
→ 乾燥の 最後の5分だけ「冷風モード」 にすると、ふんわり仕上がりますよ!
② 浴室を清潔に!カビ防止の裏ワザ
浴室は 湿気がたまりやすく、カビが生えやすい場所 です。
「こまめに掃除しても、すぐにカビが出る…」という方は、 浴室乾燥機をカビ対策に活用 してみましょう!
✅ 浴室乾燥機でカビを防ぐ方法
1. お風呂を使った後に、浴室乾燥機を1時間ほど回す
→ 湿気をしっかり飛ばして、カビの発生を防ぐ
2. お風呂の壁や床の水滴をスクイージーで取る
→ 乾燥機の効果を高める
3. カビが生えやすい場所(ゴムパッキンなど)に定期的に除菌スプレー
→ 浴室乾燥機と組み合わせるとカビ予防効果UP!
特に、梅雨の時期や冬場は湿気がこもりやすいので、 こまめに換気&乾燥をすることが大切 です。
③ 冬のお風呂が寒すぎる!を解決
冬の寒い時期、「お風呂に入るのがつらい…」と感じることはありませんか?
そんなときこそ、浴室乾燥機の 暖房機能 が大活躍します!
✅ 浴室を温める方法
1. お風呂に入る10分前から「暖房モード」をON!
→ 浴室の温度を上げて、寒さを和らげる
2. ヒートショック対策にも◎
→ 冬場、急に寒い浴室に入ると 血圧が急上昇し、体に負担がかかる ことがあります。
浴室暖房を使うことで、 温度差を減らし、安全に入浴できる のもメリット!
特に 小さなお子さんや高齢者がいる家庭では、浴室暖房を活用するのがオススメ です。
④ 夏の暑いお風呂を涼しくする方法
「冬は寒いけど、夏のお風呂は暑すぎる…!」という悩みもありますよね。
そんなときは、浴室乾燥機の 「涼風モード」 を使いましょう!
✅ 夏の入浴時の暑さ対策
• お風呂に入る 5分前に「涼風モード」をON
→ 浴室の温度が下がり、快適に入浴できる
• 入浴後にも 「涼風モード」を使うと、湿気がこもらずカビ対策にも◎
特に エアコンのないお風呂場 では、涼風モードが大活躍します!
便利な浴室乾燥機ですが、使う前に デメリット も知っておきましょう。
① 電気代が高い
浴室乾燥機は 消費電力が高め です。
例えば、 1時間使うと約30~50円、3時間で100円程度 の電気代がかかることも。
✔ 節約するには?
• 短時間で乾かす工夫(サーキュレーターの併用)
• 時間帯割引のある電力プランを活用
② フィルター掃除が必要
浴室乾燥機のフィルターにホコリが溜まると、 乾燥効率が悪くなり、電気代もUP!
✔ 1か月に1回はフィルター掃除をするのが理想 です。
③ 乾燥機の寿命は10~15年
浴室乾燥機は 10~15年が寿命 と言われています。
✔ こまめなメンテナンスで長持ちさせるのがポイント!
浴室乾燥機は 洗濯物を乾かす以外にも、さまざまな使い方ができる便利なアイテム!
あまり知られていない便利な使い方
✅ 洗濯物を 効率よく乾かすコツ
✅ 浴室のカビ対策 に活用!
✅ 冬の浴室暖房 で寒さを防ぐ
✅ 夏の涼風モード で暑さ対策
デメリットもチェック!
⚠ 電気代が高いので、節約しながら使う工夫を!
⚠ フィルター掃除を怠ると、性能が落ちる
これから浴室乾燥機をもっと活用したい方は、ぜひ この便利な使い方を試してみてくださいね!
この記事をご覧になって、ご自宅のマンションリフォームや電気工事についてご質問やご相談がございましたら、ぜひ当社ウェブサイトの「お問い合わせフォーム」よりお気軽にご連絡ください。地域や事情管理のチェックポイント、施工費用の目安などを含めて、最適なプランをご提案させていただきます。どんな小さなことでも、ぜひご相談ください。
はじめに
こんにちわ、練馬区桜台の電気工事会社「株式会社KOI-DEN」です。
家の中にある パソコンやゲーム機、スマホの充電器 などに必ず付いている 「ACアダプター」。
コンセントに差して使う黒い箱のようなものですが、実際に この中で何が起こっているか を考えたことはありますか?
「ただ電気を送るためのものじゃないの?」と思うかもしれませんが、実は ACアダプターは電気の「変換装置」 なのです!
この変換があるからこそ、私たちは安心して電子機器を使うことができます。
では、具体的にどんな仕組みで動いているのか? 今回は 「専門知識がなくてもわかる!」 をモットーに、ACアダプターの内部の働きを解説していきます!
① 電圧を変える(高い電圧 → 低い電圧)
家庭のコンセントから出る電気は 「100V(ボルト)」 ですが、パソコンやゲーム機が直接100Vで動いているわけではありません。
ほとんどの電子機器は、
✔ スマホなら 5V(ボルト)
✔ ノートパソコンなら 19V
✔ ゲーム機なら 12V など、
それぞれ 適切な電圧 が決まっています。
もしこの電圧が合っていなかったらどうなるでしょう?
例えば、スマホに 100Vの電気をそのまま流すと…
→ 一瞬でショートして壊れてしまいます!!
そこで ACアダプターが電圧を下げる役割 を果たしています。
つまり、ACアダプターは 「100V → 5V(スマホ用)」や「100V → 19V(パソコン用)」など、機器に合った電圧に変換している」 のです!
② 交流(AC)を直流(DC)に変換する
電気には 「交流(AC)」と「直流(DC)」 の2種類があります。
電気の種類 特徴 例
交流(AC) 電気の流れる方向が1秒間に50~60回変わる 家庭のコンセント(100V)
直流(DC) 電気の流れる方向が一定 スマホ・パソコン・テレビ・ゲーム機
家庭のコンセントから出てくる 100Vの電気は「交流(AC)」 ですが、スマホやパソコン、ゲーム機は 「直流(DC)」じゃないと動きません!
つまり、ACアダプターには
✅ 交流(AC) → 直流(DC)へ変換する役割 があるんです!
これを 「整流(せいりゅう)」 といいます。
③ 電気を安定させて、安全に届ける
電気は 常に一定の量で流れているわけではありません。
例えば、同じ家の中で エアコンや電子レンジを使うと、一時的に電圧が変動 することがあります。
もし スマホやパソコンに不安定な電気がそのまま流れたら…
→ 機械が誤作動を起こしたり、壊れたりしてしまいます!
そこでACアダプターは、電圧を調整しながら、安定した電気を供給してくれるのです。
ACアダプターの中身ってどうなっているの?
では、ACアダプターの内部には何が入っているのでしょうか?
実は、次のような 3つの重要な部品 で成り立っています。
① トランス(変圧器)
電圧を変えるための コイル状の部品 です。
ここで 「100V → 5V」や「100V → 19V」などの電圧変換 が行われます。
② 整流回路
交流(AC)を直流(DC)に変換するための部品です。
主に 「ダイオード」 という部品が使われていて、電気の流れる方向を一定に整えます。
③ コンデンサ(安定装置)
電気を安定させるための部品です。
コンデンサは 「電気のクッション材」 のような役割をして、電圧が急に変化しないように調整します。
ACアダプターって、パソコン用・ゲーム機用・スマホ用など、それぞれ 違うもの が必要ですよね。
その理由は 「電圧と電流(アンペア)」が機器によって異なるから です。
例えば、
✅ スマホ用のACアダプター → 5V / 2A
✅ ノートパソコン用のACアダプター → 19V / 4.7A
このように、機器ごとに必要な電圧・電流が違うので、 適切なACアダプターを使わないと故障する ことがあります!
① 適正な電圧・電流を守る
ACアダプターを選ぶときは、必ず機器に合った電圧・電流のものを使いましょう!
違うものを使うと、
❌ 電圧が低すぎる → 電源が入らない
❌ 電圧が高すぎる → 故障や発火の危険
② 純正品を使うのがベスト
安い互換品のACアダプターが売られていますが、純正品に比べて 電圧の安定性が低い ことがあります。
特に パソコンやゲーム機は精密機器 なので、できるだけ メーカー純正品を使うのが安心 です。
③ 発熱に注意!
ACアダプターは 電気を変換するときに熱を持つ ため、長時間の使用で 発熱しすぎることがあります。
⚠ 布団の上や狭い場所に置かない!
⚠ 異常に熱くなっていたら交換を検討!
今回は、ACアダプターの中で何が起こっているのかを解説しました!
✅ ACアダプターは電圧を変え、交流(AC)を直流(DC)に変換する装置!
✅ トランス・整流回路・コンデンサが重要な役割を果たしている!
✅ 適切な電圧・電流のACアダプターを使うことが大切!
普段何気なく使っているACアダプターですが、実は とても大切な役割 をしていることが分かりましたね!
これからは、ちょっと意識してACアダプターを使ってみてください!
この記事をご覧になって、ご自宅のマンションリフォームや電気工事についてご質問やご相談がございましたら、ぜひ当社ウェブサイトの「お問い合わせフォーム」よりお気軽にご連絡ください。地域や事情管理のチェックポイント、施工費用の目安などを含めて、最適なプランをご提案させていただきます。どんな小さなことでも、ぜひご相談ください。
こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社KOI-DEN」です。
普段、私たちが当たり前のように使っている電気。照明や家電がスムーズに動いているのは、家庭に適した電気の供給方式があるからです。
ところで、皆さんのご自宅の電気が 「単相2線式」 なのか 「単相3線式」 なのか、ご存じですか?
「え、そんなの考えたこともない!」という方がほとんどかもしれませんね。でも実は、この 「単相2線式」と「単相3線式」には大きな違い があり、電気の使い勝手や電気代にも影響するんです。
この記事では、家庭用の電気の仕組みについて、できるだけわかりやすく解説していきます!
特に「単相3線式」には メリットがたくさん あるので、これから家を建てる方や、リフォームを考えている方はぜひチェックしてくださいね。
まず、家の電気の仕組みを簡単に説明しましょう。
家庭の電気は 「単相(たんそう)」 という種類の電気が送られてきます。
この単相には、2つの配線方式があります。
1. 単相2線式(たんそうにせんしき)
単相2線式は、電柱から家まで 「電線が2本」 でつながっている配線方式です。
特徴
• 電圧は100V(家庭用コンセントと同じ)
• 比較的古い住宅に多い
• 使える電力量が少なめ
• 200Vの電化製品は使えない(IHクッキングヒーター、エアコンの一部など)
単相2線式のイメージ
• 電柱 → 【電線A】 → 家
• 電柱 → 【電線B】 → 家
この2本の電線で電気を供給しています。
2. 単相3線式(たんそうさんせんしき)
一方、単相3線式は 「電線が3本」 でつながっている配線方式です。
特徴
• 100Vと200Vの両方が使える
• 新しい住宅やオール電化の家では標準
• 家電がたくさんあっても、ブレーカーが落ちにくい
• 将来的な家電の増設に対応しやすい
単相3線式のイメージ
• 電柱 → 【電線A】 → 家
• 電柱 → 【電線B】 → 家
• 電柱 → 【中性線(ニュートラル)】 → 家
この3本の電線をうまく組み合わせることで、 100Vだけでなく200Vの電気も利用できる のが最大のポイントです!
では、単相3線式のメリットを詳しく見ていきましょう!
① 200Vの家電が使える!
「うちのIHクッキングヒーター、200Vだから…」
こんな会話を聞いたことはありませんか?実は、 IHクッキングヒーター、エアコン、食洗機などの一部の家電は200Vが必要 なんです。
200Vの家電は パワーが強く、効率が良い のが特徴です。例えば、
• IHクッキングヒーター → 火力が強く、調理が早い
• エアコン(大型機種) → より広い部屋を冷やせる
• 食洗機 → 洗浄力がアップ
単相2線式の家では200Vが使えないので、これらの家電を導入できません。
でも、単相3線式なら 100Vと200Vの両方が使える ので、将来的に家電を増やしたいときも安心ですね!
② 電気の使いすぎでブレーカーが落ちにくい
「電子レンジとドライヤーを同時に使ったら、ブレーカーが落ちた…」
こんな経験はありませんか?これは 電気の容量オーバー で起こります。
単相2線式は 最大30A~40A程度 の電気しか使えません。でも、家の電気使用量が増えると ブレーカーが頻繁に落ちてしまう んです。
一方、単相3線式は 50A~60A以上の契約も可能 なので、 家電をたくさん使ってもブレーカーが落ちにくい!
特に、電気を多く使う オール電化の家庭 では、 単相3線式が必須 になります。
③ 電気代が安くなる可能性がある
「え、電気の配線方式で電気代が変わるの?」と思うかもしれませんが、 単相3線式の方が電気代を節約できる可能性 があります。
なぜなら、 200Vの電化製品は100Vよりも効率が良い からです!
例えば、エアコンを200Vにすると、同じ暖房・冷房でも消費電力が減り、結果的に電気代が下がることがあります。
また、 電力会社の契約プランによっては、200Vを使うと基本料金が下がるケース もあるので、チェックしてみる価値はありますね!
「うちの家、単相2線式?それとも単相3線式?」と気になった方へ。
自宅の配線方式は 電力メーター(電力量計)や分電盤(ブレーカー)の表示を確認 すれば分かります!
確認方法
1. 電力メーターをチェック
• 単相3線式なら「単3」や「単相3線」などの表記がある
• 電線が3本あるか確認(難しい場合は電力会社に問い合わせ)
2. 分電盤をチェック
• 「200V」と書かれたブレーカーがあれば、単相3線式の可能性が高い
3. 電力会社に問い合わせる
• 確実に知りたい場合は、契約している電力会社に確認すると確実!
今回は 単相2線式と単相3線式の違い、そして単相3線式のメリット について解説しました!
単相3線式のメリット
✅ 200Vの家電が使える!
✅ ブレーカーが落ちにくい!
✅ 電気代が安くなるかも!
特に、 オール電化の家庭やこれから家を建てる人 には、単相3線式がオススメです。
「うちの電気、どうなってるんだろう?」と思った方は、ぜひチェックしてみてくださいね!
この記事をご覧になって、ご自宅のマンションリフォームや電気工事についてご質問やご相談がございましたら、ぜひ当社ウェブサイトの「お問い合わせフォーム」よりお気軽にご連絡ください。地域や事情管理のチェックポイント、施工費用の目安などを含めて、最適なプランをご提案させていただきます。どんな小さなことでも、ぜひご相談ください。
「電源コードをぐるぐる巻きにしておくと電磁波が発生して、頭に悪影響がある」
こんな噂を聞いたことはありませんか?
特に、家の中で延長コードを使うことが多い専業主婦の皆さんにとって、電磁波が健康に悪影響を与えるかどうかは気になるところですよね。実際、テレビやネットでも「電磁波が体に悪い」という話を耳にすることがあります。
そこで今回は、電源コードの巻き方によって電磁波が発生するのか、そして本当に健康に影響があるのかを、科学的な視点から解説します!
電磁波とは?

電磁波とは、電気と磁気が組み合わさった波のことです。普段の生活の中でも、私たちはさまざまな種類の電磁波に囲まれています。
例えば、以下のようなものもすべて電磁波の一種です。
✅ 可視光線(太陽の光)
✅ 赤外線(リモコンや電気ヒーター)
✅ 電波(スマホ・Wi-Fi・ラジオ)
✅ X線(病院のレントゲン)
これらは波長の違いによって分類され、**人体に影響があるのは「電離放射線」と呼ばれる強いエネルギーを持つもの(X線やガンマ線)**だけです。
一方で、電源コードから発生する電磁波は「低周波の電磁波」であり、人体への影響はほぼないとされています。
電流が流れると、電磁波は発生する
まず、電源コードに電流が流れると、必ず電磁波(電場+磁場)が発生します。これは電気の基本的な性質なので避けることはできません。
ただし、問題となるのは「コードを巻くことで電磁波が増幅するかどうか」です。
コードを巻くと電磁波は強くなる?
結論からいうと、コードを巻くことで磁場が多少強くなることはあるが、人体に影響を与えるほどではないと考えられます。
その理由は、電気が流れるときに発生する磁場は、周りの環境によって大きく影響を受けるからです。
• 通常の直線状のコードでは、磁場は広がりながら弱まる
• 巻かれたコードでは、磁場が局所的に集中する
つまり、巻いたコードの近くでは磁場がやや強くなる可能性がありますが、それが人体に影響を与えるほどの強さになることはありません。
ここで気になるのが、「電磁波を浴び続けると頭がおかしくなる」という噂です。

電磁波が人体に与える影響
科学的な研究では、通常の家庭用電源(50Hz・60Hz)から発生する電磁波が、脳や精神に悪影響を与えるという明確な証拠はありません。
ただし、一部の人々は「電磁波過敏症」と呼ばれる症状を訴えることがあります。
✅ 頭痛やめまい
✅ 集中力の低下
✅ 不眠
これらの症状が、電磁波によるものかどうかは、まだ医学的に証明されていません。むしろ、電磁波が気になることでストレスが生じ、それが原因で体調を崩す可能性のほうが高いと考えられています。
電磁波の影響を心配するよりも、実際に家庭内で起こる電気トラブルのリスクに注意を向けるほうが現実的です。
① コードをぐるぐる巻きにすると発熱のリスクがある!
コードを巻いて使うこと自体が直接電磁波を強くするわけではありませんが、巻きすぎると発熱するリスクがあります。
特に、電力を多く消費する家電(電子レンジ・エアコンなど)のコードを束ねると、熱がこもり火災の原因になることも!
🔹 コードを使うときのポイント
✔ 束ねずにできるだけ伸ばして使用する
✔ 電力の大きな家電は専用コンセントを使う
✔ 長期間使わないときはコンセントを抜く
② ほこりがたまると「トラッキング火災」が発生することも!
コンセント周りにほこりがたまると、ショートして火災が発生することがあります。
🔹 対策方法
✔ 定期的に掃除機でほこりを吸い取る
✔ 使っていないコンセントはカバーをつける
結論として、コードをぐるぐる巻きにすることで発生する電磁波が人体に害を与えることはありません。

✅ 家庭の電源コードから発生する電磁波は極めて弱い
✅ コードを巻くと磁場が集中することはあるが、人体への影響はほぼない
✅ 「頭がおかしくなる」という噂は科学的根拠がない
✅ しかし、巻きすぎると発熱・火災のリスクがあるため注意!
むしろ、気をつけるべきなのは、電気コードの正しい使い方です。
特に発熱やトラッキング火災などのリスクを防ぐために、日頃からコードの管理をしっかりしておきましょう!
このような電気に関する疑問をしっかり理解して、安全に暮らすことが大切ですね。
この記事をご覧になって、ご自宅のマンションリフォームや電気工事についてご質問やご相談がございましたら、ぜひ当社ウェブサイトの「お問い合わせフォーム」よりお気軽にご連絡ください。地域や事情管理のチェックポイント、施工費用の目安などを含めて、最適なプランをご提案させていただきます。どんな小さなことでも、ぜひご相談ください。
家の中には数多くのコンセントがありますが、意外とその形状や用途について詳しく知っている人は少ないかもしれません。
「このコンセントって普通のプラグ以外にも使えるの?」
「キッチンのコンセント、普通のと何が違うの?」
特に専業主婦の方にとって、キッチン・リビング・寝室など家庭内のコンセントを安全に使うことはとても重要です。知らずに間違った使い方をすると、漏電や火災の原因にもなりかねません。
そこで今回は、家庭内でよく使われるコンセントの形状と用途について詳しく解説します!
① 一般的な「平行型コンセント」
家庭で最も多く使われているのが、2本の平行な差込口を持つコンセントです。
🔹 用途:スマホの充電器、炊飯器、テレビなどの家電
🔹 特徴:どんな家庭にもあり、最も一般的なタイプ
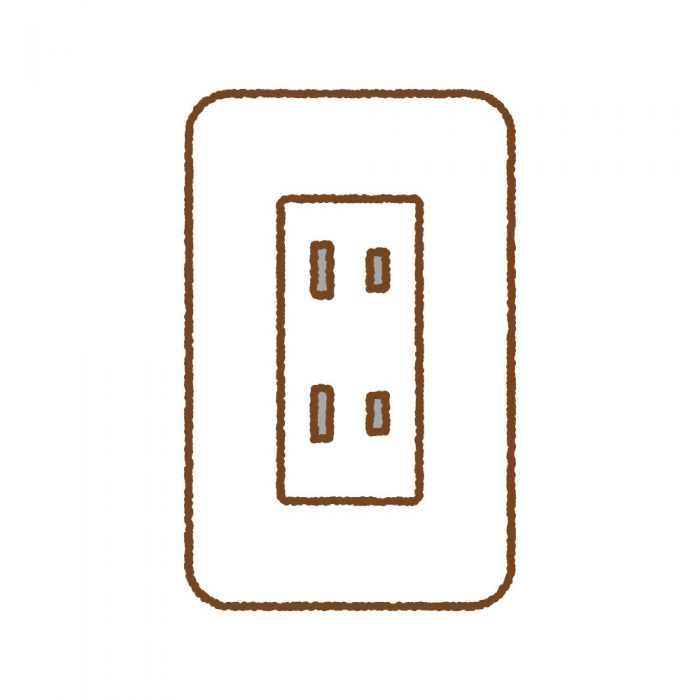
② アース付き「接地極付きコンセント」(3つ穴タイプ)
冷蔵庫や電子レンジのコンセントをよく見ると、2つの穴に加えて下部に丸い穴があることに気づきませんか?これは「接地極付きコンセント」といって、アース線を接続できるようになっています。
🔹 用途:冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコンなど
🔹 特徴:電気の漏れを防ぎ、感電事故を防止

アースの役割とは?
万が一、電気が漏れたときに電気を地面へ逃がし、感電を防ぐ役割があります。特に水回り(キッチン・洗面所・洗濯機周辺)では必須です!
③ 200V対応のコンセント(エアコン専用)
通常のコンセントは100Vですが、大型のエアコンや業務用機器では200Vのコンセントが必要になることがあります。
🔹 用途:エアコン、IHクッキングヒーターなど
🔹 特徴:プラグの形状が特殊で、通常の100V家電は使えない

※200Vのコンセントを使用するには、専用の電気工事が必要です。無理に100Vの家電を接続しないよう注意しましょう!
① USBポート付きコンセント
最近では、コンセントに直接USBポートが付いているタイプも増えています。
🔹 用途:スマホ・タブレット・モバイルバッテリーの充電
🔹 特徴:アダプター不要で、直接USBケーブルを挿して使える

便利ポイント!
・スマホの充電器を探さなくても、すぐに充電できる
・家族みんなで同時に充電が可能
② 屋外用コンセント(防水仕様)
庭やベランダで使われる防水仕様のコンセントもあります。
🔹 用途:屋外照明、電動工具、洗車用高圧洗浄機
🔹 特徴:防水カバーがついていて、水が入らない設計

※雨の日にむき出しのコンセントを使うと危険! 必ず防水タイプを使用しましょう。
③ テーブルタップ(延長コード)を正しく使う
家庭内でコンセントの数が足りないときに**延長コード(テーブルタップ)**を使うことがあります。
🔹 用途:デスク周りのPC、テレビ周辺の家電
🔹 特徴:コンセントを増やせるが、使い方を間違えると火災の原因に!

安全に使うポイント!
✔ ワット数を守る(タコ足配線は危険)
✔ コードを束ねない(熱がこもり火災の原因)
✔ 定期的に掃除する(ほこりが溜まると発火リスク)
コンセントのトラブルは意外と身近にあります。日常的に注意すべきポイントをチェックしましょう。
① ほこりがたまると「トラッキング現象」で火災の危険!
コンセントの隙間にたまったほこりが原因で、ショートして発火することがあります。

対策
🔹 定期的に掃除機で吸い取る
🔹 使っていないコンセントにはカバーをつける
② 子どもがいる家庭では「コンセントキャップ」を活用
小さな子どもは、コンセントの穴にものを入れたがることがあります。感電事故を防ぐために**「コンセントキャップ」**を使いましょう!
③ 長期間使用していないコンセントはチェックする
古いコンセントは劣化していることも。黒ずんでいたり、焦げた臭いがする場合は要注意!
➡ 電気工事士に相談しましょう!
最後に、家の中で「もっと便利にコンセントを活用する方法」をご紹介します!
✔ リビングのソファ周りに「フロアコンセント」
→ スマホの充電や掃除機を使うときに便利!

✔ キッチンには「スライド式コンセント」
→ 使わないときは収納でき、調理中の邪魔にならない

✔ 寝室には「タイマー付きコンセント」
→ 寝る前の電気毛布や加湿器におすすめ!

✅ 家庭にあるコンセントの種類を理解しよう!
✅ アース付きコンセントは必須!特に水回りでは注意!
✅ USBコンセントや防水コンセントなど便利な種類もある
✅ 定期的な掃除と点検で、火災や漏電を防ぐ
✅ 子どもやペットがいる家庭では安全対策を!
コンセントは毎日使うものだからこそ、正しく理解し、安全に活用することが大切です。
今日からでもすぐにできる対策を取り入れて、安心・快適な暮らしを目指しましょう!
この記事をご覧になって、ご自宅のマンションリフォームや電気工事についてご質問やご相談がございましたら、ぜひ当社ウェブサイトの「お問い合わせフォーム」よりお気軽にご連絡ください。地域や事情管理のチェックポイント、施工費用の目安などを含めて、最適なプランをご提案させていただきます。どんな小さなことでも、ぜひご相談ください。
冬場の「バチッ!」に困っていませんか?
冬場になると、ドアノブや衣類を触ったときに「バチッ!」とくる静電気。特に乾燥した季節には頻繁に起こり、不快な思いをすることも多いですよね。
「この静電気、どうにかならないの?」
「電気工事士さんなら対処法を知っているのでは?」
そんな疑問を持つ皆さんへ、電気工事士だけが知っている「静電気の正体」と「簡単にできる対策」をお伝えします!
静電気の正体

静電気は、物質同士がこすれ合うことで生じる「電荷の偏り」によるものです。簡単にいうと、物の表面にたまった電気が、一気に放電される現象があの「バチッ!」という感覚です。
例えば、以下のような場面で静電気は発生します。
✅ 衣類を脱ぐときにパチパチする → 服同士の摩擦による帯電
✅ ドアノブを触った瞬間にバチッ! → 体にたまった電気が金属に流れる
✅ 車のドアを開けるときにビリッ! → 座席の布と体がこすれて電気が発生

特に、冬場や乾燥した季節にはこの静電気が発生しやすくなります。なぜなら、空気中の水分が少ないと、電気が逃げにくくなるからです。
静電気が起こりやすい環境にはいくつかの共通点があります。
① 乾燥している環境
冬場やエアコンの効いた部屋では、湿度が低いため静電気が発生しやすくなります。

② 化学繊維の服を着ている
ナイロンやポリエステルなどの化学繊維は、静電気をため込みやすい性質を持っています。逆に、綿やウールなどの天然素材は静電気が発生しにくいです。
③ 金属に触れる瞬間
ドアノブや車のドアなどの金属は電気を通しやすく、体にたまった静電気が一気に流れて「バチッ!」と感じます。
「じゃあ、どうやって防げばいいの?」と思った方へ、次に簡単な対策方法を紹介します!
① 部屋の湿度を上げる
静電気は乾燥していると発生しやすいため、加湿をすることが最も効果的です。
🔹 加湿器を使う → 湿度50%以上を目安に
🔹 濡れたタオルを干す → 手軽な加湿方法
🔹 観葉植物を置く → 自然な湿度調整

特に、寝室やリビングの乾燥がひどいと静電気が発生しやすくなるため、湿度管理を意識しましょう。
② 綿やウールの服を着る
化学繊維の服は静電気をためやすいため、できるだけ綿やウールなどの天然素材を選ぶと良いでしょう。
特に、肌に直接触れるインナーを綿にすると、静電気が軽減されます。
③ 金属に触れる前に放電する
ドアノブや車のドアを触る前に、以下のような方法で静電気を逃がしましょう。
🔹 壁や木の家具に触れる → ゆっくり電気を逃がせる
🔹 鍵や金属製のものを持ってから触る → 鍵をドアノブに当てて放電
🔹 ハンドクリームを塗る → 静電気をためにくくする
特に、ハンドクリームは乾燥対策にもなるので、女性にとっては嬉しい対策ですね!
市販されている静電気防止グッズを使うのもおすすめです。
✅ 静電気除去シート(車のドアに貼るだけ)
✅ 静電気防止スプレー(服やソファに吹きかける)
✅ 静電気防止ブレスレット(身につけるだけ)
100円ショップでも手に入るアイテムが多いので、気軽に試してみてください!
「家の中で静電気がひどい…」「家電が頻繁にビリビリする…」という場合、実は漏電の可能性があるかもしれません。
✅ 特定の家電を触ると静電気を感じる
✅ 夜、蛍光灯がチラつく
✅ ブレーカーがよく落ちる
このような症状がある場合は、電気工事士に点検を依頼しましょう。静電気と思っていたものが、実は電気配線の問題だった…ということもあり得ます。
練馬区周辺で電気工事をお探しの方は、お近くの業者に相談してみるのもおすすめです。
✅ 静電気は「乾燥」と「化学繊維」によって発生しやすい
✅ 部屋の湿度を上げることで軽減できる
✅ 綿やウールの服を選ぶと静電気を防げる
✅ 金属に触れる前に木や壁に触れて放電
✅ 静電気防止グッズを活用するのも◎
静電気はちょっとした工夫で防げるものです!
ぜひ今日から対策を始めて、快適な冬を過ごしてくださいね。
もし、家の中の電気トラブルが気になる場合は、電気工事士に相談するのも一つの方法です。安全で快適な生活を送るために、ぜひこの情報を役立ててください!
この記事をご覧になって、ご自宅のマンションリフォームや電気工事についてご質問やご相談がございましたら、ぜひ当社ウェブサイトの「お問い合わせフォーム」よりお気軽にご連絡ください。地域や事情管理のチェックポイント、施工費用の目安などを含めて、最適なプランをご提案させていただきます。どんな小さなことでも、ぜひご相談ください。
こんにちは。練馬区桜台のリフォームに強い電気工事会社、株式会社コイデンです。
練馬区にお住まいの主婦の皆様へ
毎日の家事や生活の中で、家の電気に関するトラブルは突然発生します。特に「漏電」は放っておくと火災の原因にもなりかねません。
でも、大丈夫!特別な知識がなくても、自宅で簡単にできる漏電チェックと応急処置の方法を分かりやすく解説します。
今回は、以下の5つのポイントで説明していきます。
1. そもそも漏電とは?基本知識を押さえよう
2. こんな症状に注意!漏電のサインとは
3. 自宅でできる簡単な漏電チェック方法
4. 緊急時の応急処置とブレーカーの操作方法
5. プロに相談すべきケースと業者の選び方
この記事を読むことで、万が一の時に冷静に対処できるようになります!
まず「漏電」という言葉をよく耳にしますが、具体的にどういう現象かご存知でしょうか?
本来、電気は電線や電気機器の内部を通るものですが、配線の損傷や設備の劣化によって、電気が本来のルート以外に流れてしまう現象を「漏電」と言います。
漏電を放置すると、次のようなリスクがあります。
• 感電の危険性:濡れた手でスイッチを触るとビリッとくることも。
• 火災のリスク:長期間放置すると発熱し、火災につながることも。
• 電気代の無駄:見えない場所で電気が流れ続け、電気料金が増加することも。
「でも、どこが漏電しているのか分からない…」
次の章で、漏電が発生しているかどうかを見分ける方法を解説します!
漏電は目に見えないため、発見が遅れることがよくあります。以下のような症状が出たら、要注意です!
✅ ブレーカーが頻繁に落ちる
• 突然電気が消え、ブレーカーを上げてもすぐにまた落ちる場合は、漏電の可能性が高いです。
✅ 特定のコンセントやスイッチが熱い
• 手で触ると温かく感じる場合は、内部で漏電している可能性があります。
✅ 電気料金が急に高くなった
• 使っていないのに電気料金が急増しているなら、漏電によって無駄な電気が流れ続けている可能性があります。
✅ 感電のようなピリッとした刺激を感じる
• 家電やスイッチを触った時に、ビリッとするなら要注意!
✅ 電気の匂いがする、焦げ臭い
• 配線がショートしている可能性があり、火災の危険もあるため、すぐに対応が必要です。
「このような症状があったら、すぐに確認を!」
次の章で、自分でできる漏電チェックの方法をお伝えします!
専門業者に依頼する前に、自分でできる簡単なチェック方法を試してみましょう!
漏電チェックの手順
1. ブレーカーの「漏電遮断器」を確認する
• 家の分電盤を開き、「漏電遮断器」(通常、一番左にあるブレーカー)が落ちているかチェック。
• 落ちていた場合は、漏電が発生している可能性大。
2. 家中のブレーカーを一度すべてオフにする
• 各部屋のブレーカーをオフにした状態で、「漏電遮断器」をオンにする。
3. 1つずつブレーカーを戻してチェック
• 1つずつブレーカーを上げながら、どの部屋でブレーカーが落ちるか確認する。
• 特定の部屋のブレーカーを上げた瞬間に落ちたら、その部屋が漏電の原因。
4. 原因となる家電を特定する
• その部屋のコンセントをすべて抜き、再度ブレーカーを上げる。
• その後、1つずつ家電をコンセントに挿し、どの家電でブレーカーが落ちるか確認する。
「原因が分かったら、次は応急処置です!」
まず最優先は安全確保!
✔️ 素手で触らない(必ずゴム手袋を使う)
✔️ 水をかけない(水は電気を通すため感電リスクあり)
✔️ すぐにブレーカーをオフにする
ブレーカーの正しい操作方法
1. 漏電遮断器をオフにする
2. 原因となる部屋のブレーカーをオフにする
3. 安全が確認できるまで、その部屋の電気を使わない
「でも、自分ではどうにもできない…」
その場合は、すぐに専門業者に相談しましょう!弊社へのお問い合わせはこちら
以下のような場合は、自分で対応せずに業者へ依頼しましょう。
✅ 漏電の原因が分からない
✅ ブレーカーを戻してもすぐに落ちる
✅ 焦げ臭い匂いがする
信頼できる業者を選ぶポイント
• 練馬区の地域密着型の電気工事会社に依頼する(素早い対応が期待できる)
• 口コミや評判をチェック(GoogleやSNSのレビューを確認)
• 見積もりを事前に確認(追加料金がかからないか要チェック)
✅ ブレーカーが頻繁に落ちる場合は要注意!
✅ 簡単なチェックで漏電の原因を特定できる
✅ 緊急時はブレーカーを落とし、安全確保が最優先
✅ 専門業者に早めに相談することが大切
練馬区で漏電トラブルにお困りの方は、地域密着の電気工事業者へご相談を!
安全な暮らしのために、今すぐチェックしてみましょう。
この記事をご覧になって、ご自宅のマンションリフォームや電気工事についてご質問やご相談がございましたら、ぜひ当社ウェブサイトの「お問い合わせフォーム」よりお気軽にご連絡ください。地域や事情管理のチェックポイント、施工費用の目安などを含めて、最適なプランをご提案させていただきます。どんな小さなことでも、ぜひご相談ください。
皆さん、こんにちは。練馬区の電気工事会社「株式会社コイデン」です。
おうちのリフォームを検討するとき、キッチン・バスルームなどの水回りや、壁紙、床材といった「見た目の変化」を重視される方が多いかもしれません。しかし、住まいの安心感や使い勝手を大きく左右する電気工事も、同時に見直しておくことがとても大切です。
特に練馬区は、都内の中でも戸建て住宅や築年数の経ったマンションが多く、ライフステージの変化に合わせてリフォームを考える主婦の方も少なくありません。たとえば、子ども部屋にエアコンを増設したい、キッチンを省エネ家電に変えたい、あるいはリビングの照明をLED化したいといった要望が出てきたとき、必ず関わってくるのが電気工事です。
電気工事は配線やブレーカーなど、普段目にしにくい部分の施工が中心となりますが、ここをおろそかにするとブレーカーが頻繁に落ちる、電気代が無駄にかかる、さらには火災のリスクを高めるなど、トラブルの原因にもなりかねません。また、主婦の目線で重要なのは、日々の家事で使うアイロンや掃除機、キッチン家電などがスムーズに使えるかどうか。コンセントの位置や数が適切でなければ、毎日の生活が小さなストレスの連続になってしまいます。
このように、快適かつ安全な住まいを実現するうえで欠かせない電気工事。次のブロックでは、見積もりを依頼する前にチェックしておきたいポイントを詳しくご紹介します。「どこまでやってもらうべき?」「予算はどう考えればいい?」などの疑問も含めて解決していきましょう。

電気工事の見積もりを依頼する前に、まずは基礎用語を簡単に押さえておきましょう。
たとえば「回路を増やす」とは、家の中の電気配線をどのように分けるかを調整すること。
「アンペア数を上げる」とは、同時に使える電力量を増やすことでブレーカーが落ちにくくする工事を指します。
さらに「コンセントを増設する」場合は、壁や床下を開口して配線を延長する作業が必要になることもあるため、費用や工期に影響する点を把握しておきましょう。
また、リフォーム全体の予算を決める際、キッチンやバスルームなど、見た目や機能が大きく変わる場所にばかり目が行きがちです。しかし、電気工事に十分な予算を確保しておかないと、工事中に「古い配線が使えず急遽交換が必要」と判明し、予定外の出費がかさむケースが少なくありません。事前に業者と相談し、どの程度の工事が必要なのかを大まかに把握しておくことが重要です。
最後に、家族構成や生活スタイルを整理しておくと、見積もりの際に具体的な要望を伝えやすくなります。「子どもが成長してスマホやタブレットを使う」「在宅ワークを長期的に考えている」「調理家電が増える予定」などの情報は、コンセントや回路をどう増やすかの判断材料になります。リフォームの機会に、今後のライフプランまで考慮した電気工事を行っておくことで、長く快適に暮らせる住まいを手に入れましょう。
電気工事を依頼する際にまず注目していただきたいのは、練馬区など地元エリアに根ざした業者かどうかという点です。地元密着の企業は、地域特有の住宅事情に精通していたり、自治体や管理組合とのやり取りに慣れているなどの強みがあります。また、アフターサポートやトラブル対応のスピードが速いのもメリット。もし何か不具合があったときでも、すぐに駆けつけてくれる安心感は大きいでしょう。
次に重要なのが、評判や口コミのチェックです。インターネットの検索やSNS、あるいは練馬区のママ友・ご近所コミュニティなどから、実際に工事を依頼した人の声を集めてみましょう。ただし、ネット上の口コミは玉石混交なので、あまりに一方的な内容や、過度に高評価・低評価だけのレビューは注意が必要です。複数の情報源を比較し、総合的に判断することをおすすめします。
そして、電気工事士の資格の有無や保証制度の内容も業者選びでは欠かせないポイントです。電気工事士資格を持つスタッフが常駐しているか、万が一の事故に備えて賠償保険に加入しているかなどを確認しておくと、いざというときに安心して任せられます。特にリフォーム初心者の方は、事前に細かい質問をしてもしっかり答えてくれる業者を選ぶのがベター。工事内容や見積もりの根拠などを分かりやすく説明してくれるかどうかが、信頼度の目安になります。
リフォームを進めるうえで、工期とスケジュール管理はとても重要です。特に電気工事の場合、一時的に電気を止める必要があるため、冷蔵庫や照明、エアコンなど、生活に直結する設備が使えなくなる時間帯が発生します。工事日や作業時間帯をあらかじめ把握し、料理や洗濯などのスケジュールを組み替えられるようにしておくと、家事の負担を最小限に抑えられます。
また、工事内容によっては仮住まいが必要になるケースもあります。たとえば、家全体の電気配線を大幅に変更する場合や、壁や天井を大きく開口する工事がある場合は、日中だけでなく夜間も電気が使えないことがあります。小さなお子さんや高齢のご家族がいるなら、より慎重に検討しなくてはなりません。事前にどの程度の期間、電気が使えないのかを業者と確認し、必要があれば代替の住まいを確保しましょう。
さらに、追加工事を減らすためのプランニングもポイントです。たとえば、電気工事と同時にクロスの張り替えや配管の工事を行ってしまえば、何度も壁を開ける手間や費用が省けることがあります。特に練馬区の住宅は建物自体がやや古いケースも多いので、リフォームの際にまとめてメンテナンスを済ませることを意識すると、結果的にコストを抑えられるでしょう。業者とよく相談して、どのタイミングで何を行うのがベストかを検討してみてください。
リフォームを成功させるには、複数の業者から相見積もりをとることが基本です。1社だけの見積もりでは、価格や工事内容が適正かどうか判断しづらいため、最低でも2~3社の見積もりを比較してみましょう。その際、単純な金額の安さだけでなく、工事内容の詳細や使用する部材、アフターフォローなども含めて総合的に検討することが大切です。
見積もりの内訳をチェックする際は、材料費(配線やコンセント、ブレーカーなど)、人件費、諸経費などが明確に分かれているかを確認しましょう。「諸経費」という項目にどこまで含まれているかは業者によって異なる場合があるため、不明点があれば遠慮なく質問して構いません。また、工事期間中に発生し得る追加費用の有無や、その条件も忘れずに確認しておきましょう。
最終的に契約を結ぶ前には、**書面(契約書・工事内容確認書など)**のチェックが欠かせません。業者の保証制度や保険、万が一の事故対応など、トラブルが起こった場合の対応が明記されているかをしっかり確認しましょう。特に電気工事は安全面が重要なので、資格保有者が作業を行うことや、施工後の不具合に対応する保証期間の長さなどを重視すると安心です。納得のいくまで説明を受け、疑問点が解消されてからサインすることで、後悔のないリフォームが実現します。
リフォームにおいて見落とされがちですが、電気工事は日々の暮らしの快適さや安全性を左右する大切な要素です。特に、練馬区のように築年数の経過した住宅が多い地域では、配線の老朽化やアンペア不足などの問題が起こりやすく、リフォームと同時に見直しておくことが得策といえます。
電気工事は、一度きちんと施工しておくと長く安心して暮らせる反面、後回しにすると思わぬトラブルの原因になることも。お子さんやご家族の将来まで考えたうえで、ベストなタイミングと業者を選び、快適な住まいづくりを実現してください。これからリフォームを始める方にとって、本記事が少しでも参考になれば幸いです。
この記事をご覧になって、ご自宅のマンションリフォームや電気工事についてご質問やご相談がございましたら、ぜひ当社ウェブサイトの「お問い合わせフォーム」よりお気軽にご連絡ください。地域や事情管理のチェックポイント、施工費用の目安などを含めて、最適なプランをご提案させていただきます。どんな小さなことでも、ぜひご相談ください。
練馬区桜台のリフォーム提案が強い電気工事会社「株式会社コイデン」です。
今回の記事では、練馬区在住でマンションリフォームを検討中の皆さん、特に主婦の方に向けて、今回は「マンションリフォームにおける電気工事のポイント【練馬区版】」というテーマでお話しします。
練馬区在住の主婦の皆さんの中には、立地を考慮して転居された方、子育てがひと段落した方、様々な変化がご家庭に起きている、または想定されているのではないかと思います。
「少し家の中を快適にしたい」
「大きくなってきた子どもが使いやすいようにレイアウトを変えたい」
「老後まで長く住めるように、先々を見据えてリフォームしたい」
「事故や災害などの心配がないような、安全な設備を整えたい」など、マンションリフォームに興味をお持ちの方は、きっと多いはずです。

マンションリフォームを検討する際には、見た目のや一瞬の満足だけでなく、デザイン(設計)として、忘れがちな部分に注目することも大切です。そのひとつが電気工事。
日常生活を支える電気は、コンセントの位置一つで問題や快適さが大きく変わりますし、エアコンやキッチン家電の配置が増えるだけでも長く住む上での満足度は変わります。
既存の配線が古いままだと、トラブルが生じるリスクもあります。 さらに、照明の一新やコンセント・スイッチの増設・位置変更などを含めて検討することで、お部屋の雰囲気や日々の快適性を劇的に向上させることができるます。
特に、練馬区は都内でも比較的歴史のあるベットタウン。築年数が経過している物件では、電気配線の老朽化やアンペア不足が問題になるケースが非常に多く見受けられます。実際、弊社へのご依頼の多くも「築年数が経過したマンションのリフォーム」です。
エアコンや電子レンジ、食洗機、IHクッキングヒーターなど、多くの家電を一緒に使うとブレーカーが落ちやすくなったり、故障の原因になることも少なくありません。
リフォームの機会を利用して、しっかりと電気配線を見直すことは、結果的に家族が安心して暮らせる住まいづくりに繋がります。
また、お子様の成長を見越して勉強机の周りのコンセントを増やしたり、在宅ワークが増えた旦那様のデスク周りをすっきりさせるために電源やLAN配線の整備をする、といった要望にも対応できるのが電気工事です。
今後のライフプランを視野に入れながら、「ここにあったら便利」というコンセントの位置や数をリフォーム前に検討しておくことがおすすめです。
本記事では、マンションのリフォームにおける電気工事の基本ポイントから、練馬区だからこそ押さえておきたい注意点と費用感、さらに実際にリフォームを進める際の流れやコツまで、各ブロックに分けて詳しくご紹介いたします。
マンションにお住いの主婦の方が抱く不安や疑問に寄り添いながら、わかりやすく解説してまいりますので、ぜひ最後までご覧ください。
まず、マンションリフォームにおいて電気工事がどのように行われるか、どんなメリットがあるのか見てみましょう。
リフォームの際に検討する点は多々ありますが、その中でも電気配線やコンセント、照明計画、アンペア数の見直しは非常に重要です。
マンションの電気工事は管理組合のルールに沿った工事が大前提ですが、しっかりと準備をすれば安全で快適な住まいづくりを実現してくれます。
それでは、具体的に練馬区のマンションならではの注意点や、工事費の目安などを次に見ていきましょう。
ここからは、練馬区にお住まいの主婦の方にとって、特に控えておきたい「練馬区のマンションならではの注意点」と「電気工事費用の相場感」について解説します。
例えば、コンセントの増設1か所あたりで1万円前後、照明器具の取り付けで1~2万円程度の価格帯が都内の多くの業者では主流のようですが、マンション全体で配線を新しくする場合は数十万円規模になることもあります。
また、古いマンションで天井裏のスペースが狭い場合や、壁内の配線が複雑に入り組んでいる場合は、追加工事が発生してさらに費用がかかる可能性があります。
練馬区のマンションにはファミリー世帯が非常に多いため、管理規約や周囲への配慮など、独自の事情が存在します。しかし、それらをしっかりと把握しておけば、安全性や快適性を高めるためのリフォーム工事は決して難しくありません。次のブロックでは、実際にリフォームを進める際の流れや、具体的なスケジュール管理のコツ、業者の選定などをまとめていきます。
ここまで、マンションリフォームにおける電気工事の必要性やポイント、そして練馬区ならではの注意点や費用感についてお話ししてきました。最後に、リフォーム全体を円滑に進めるためのコツや、主婦の方ならではの視点でアドバイスをまとめておきます。
など、事前に手を打っておけば、リフォームによる負担を極力抑えられます。
ここまで、練馬区在住の主婦の方を対象に「マンションリフォームにおける電気工事のポイント【練馬区版】」として、各ブロックに分けてご紹介しました。
リフォームにおいて、電気工事は見えにくい部分ではありますが、暮らしの快適性や家族の安心を大きく左右する重要な要素です。 古い配線のまま使い続けるリスクを避けるだけでなく、コンセントの増設や照明計画をしっかり行うことで、実際の生活が格段に便利になります。
また、練馬区では比較的築年数が経過したマンションも多く、管理規約との調整や大掛かりな配線工事が必要になる可能性がありますが、事前のチェックや専門業者のサポートがあれば安心して進められます。
今回お伝えしたポイントを参考にしながら、見積もりの見方やスケジュール調整、家族との連携をしっかり行うことが成功の鍵です。
これを機に、ぜひご自宅のマンションリフォームを検討してみてください。 今の暮らしをより快適に、そしてこれからも安心して住める住環境を実現するために、電気工事も含めた総合的なリフォームを一度しっかり計画してみることをおすすめします。 家事や育児をしながらのリフォームは大変なことも多いですが、その先に得られる快適さや満足度はきっと大きいはずです。家族みんなが笑顔になれる住まいづくりを、ぜひ前向きに進めてみてください。
この記事をご覧になって、ご自宅のマンションリフォームや電気工事についてご質問やご相談がございましたら、ぜひ当社ウェブサイトの「お問い合わせフォーム」よりお気軽にご連絡ください。地域や事情管理のチェックポイント、施工費用の目安などを含めて、最適なプランをご提案させていただきます。どんな小さなことでも、ぜひご相談ください。
明けましておめでとうございます。
旧年中は、株式会社コイデンをご愛顧いただき、誠にありがとうございました。皆さまの温かいご支援のおかげで、無事に新しい年を迎えることができました。
本年も引き続き、地域に根ざした電気工事サービスを通じて、皆さまの暮らしをより快適で安心なものにするお手伝いをさせていただきます。
特に、住宅の電気設備や空調機器の設置・メンテナンスにおいて、お客様の多様なニーズにお応えできるよう、技術の向上とサービスの質の向上に努めてまいります。
また、2025年は新しい取り組みとして、オンラインでのご相談受付やブログを通じた情報発信にも力を入れてまいります。節電のコツや、電気設備に関する豆知識など、皆さまの生活に役立つ情報をお届けしていきますので、ぜひご覧いただければ幸いです。
株式会社コイデンは、社員一同、お客様第一の姿勢を忘れず、信頼されるパートナーとして精一杯努めてまいります。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
最後になりますが、皆さまのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。