-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー

令和6年度に起きた電気工事の感電・死亡災害を、実際の作業シーンで7類型に分類。共通要因と現場で使える再発防止チェックを、電工目線で徹底解説します。
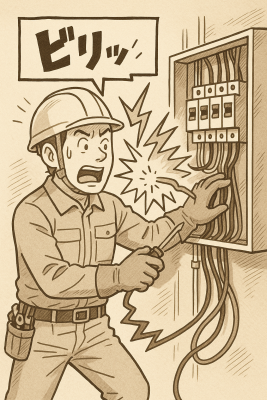
感電・電撃災害は、一つのミスで起きるのではなく、小さな抜けや思い込みが重なって発生します。とくに電気工事は、停電・検電・表示施錠・短絡接地という基本の一連(Lockout/Tagoutの和訳運用)が崩れた瞬間、命に関わります。本稿では、令和6年度の公表事例や報道傾向から、事故が集中した“作業内容”で7つに整理。各類型ごとに起こりやすい場面・共通要因・5分でできる点検リストを示します。
結論から言えば、最も多いのは**「受配電設備内の活線近接」と「送配電線路の近接・重機接触」、次いで「屋内配線の逆接・誤認」。そして下請け階層化や単独作業**がリスクを跳ね上げます。
典型シーン
伐採した枝や幹が想定外に反発・回転して活線部に近接/接触
建柱車や高所作業車のブームが離隔不足のまま旋回・上昇
現場条件(風・傾斜・周辺工作物)変化を班内で再共有しないまま続行
共通要因
離隔基準の事前算定不足(可動域・反発角・吊荷振れを含めていない)
監視員不在や合図の混乱、立入区分の曖昧化
マンネリ化(「いつも大丈夫だった」)による近接軽視
5分点検
風向・反発方向・ブーム可動域を現地で模式図化し共有
監視員の専任と立入区分(カラーコーン・バー・看板)を設置
最小離隔の読み上げ(誰が言ったか分かる声で/復唱)
重機旋回・上昇前に**“停止→指差呼称→OK合図→駆動”**を徹底
典型シーン
盤内でケーブル通線中、銅バー(通電)へ近接/接触
絶縁養生の範囲不足、配線ルート変更がその場判断
共通要因
停電計画の不徹底(計画はあっても“作業直前の検電”がない)
遮へい・養生の不足(バー・端子が見えている)
二次請け以降への手順書・図面未配布
5分点検
停電→施錠・表示→“作業直前”の検電→短絡接地を作業者本人が確認
露出充電部へ硬質養生(規格品)+立入禁止表示
図面の版数と通線ルートを、班全員で声に出して復唱
絶縁用手袋・保護具の劣化点検(ピンホール、期限、サイズ)
典型シーン
点検窓やカバーを外し、通電部が見えている状態で清掃・締付
「計器を見るだけ」「写真だけ」のつもりで接近限界を跨ぐ
共通要因
軽作業扱いで安全措置を省略
狭小盤室での姿勢変化(しゃがみ→起立)による誤接触
単独作業での判断ミス
5分点検
**“軽作業でも活線近接は同じ”**の原則を掲示
接近限界ラインの床マーキング(テープ)
片手作業・姿勢管理・工具絶縁被覆の再点検
単独作業禁止(少なくとも同席者の復唱を条件に)
典型シーン
撤去対象の一部が活線系統に残存しているのに、無電化と誤認
仮設材や押さえ金具を外した瞬間に導通ルートが変わる
共通要因
系統切替・段取り変更の口頭共有のみ
識別ラベル不足/旧ラベル残置
“終盤だから”の焦り
5分点検
撤去前に系統図へ赤入れ(残存・活線・無電の色分け)
ラベルを現場で貼り替え/旧ラベル剥離までやる
「段取り確認のみ」でも検電→接地を実施(時間を惜しまない)
典型シーン
コンセントや照明回路で電源・負荷の逆接、プラグ抜去時に電源側露出
調光器・センサ混在回路で相序/極性の思い込み
共通要因
単独作業、ラベル/回路図の不整合
既設系統の流用で検電省略
試験・通電確認の順序ミス
5分点検
極性・相序をテスター/検電器で実測→ラベル貼付
プラグ/コネクタの切り離しは**“無電確認→写真記録→抜去”**
単独作業時は電話スピーカONでの復唱手順を必須化
典型シーン
逆潮流・バックフィードの想定漏れ
PCSや蓄電池の自動再起動を失念
非常用発電機試験後の切替戻し忘れ
共通要因
元系統/非常系統/分散電源の役割と位相の理解不足
試験モード→常用の移行手順書が曖昧
ステッカーや結線図の現地整備不足
5分点検
**「全電源停止条件」**を文書化し、誰が・どこで確認するか明記
連系遮断器の位置表示(機械表示+タグ)をダブルで
試験後の復旧チェックリストを読み上げ→署名
典型シーン
仮設分電盤の漏電遮断器容量/感度不適合
コードの被覆損傷・水濡れ、養生なし
班長不在時の増し増し使用(たこ足)
共通要因
工程遅延による“とりあえず”運用
雨天対策の甘さ(屋外配線・仮設照明のIP等級軽視)
誰の管理物か不明な仮設が残置
5分点検
漏電遮断器の動作試験と適正感度の確認(記録残し)
延長コードの全長目視(被覆・コネクタ・防水)→不適合は即交換
仮設品に管理者名・撤去予定日を明記したタグを付与
情報共有の断絶
一次→二次→三次で図面・手順書の版ズレ、口頭伝達のみ、当日変更の紙残しなし。
対策:「版数」を声で確認、配布先の記名リスト運用、当日変更は必ず赤入れ+写真。
“作業直前”の検電欠落
前日に検電済み=安全ではない。人の出入り・切替・再起動で状況は変わる。
対策:停電→施錠・表示→直前検電→短絡接地を“読む・やる・記録する”。
単独作業・軽作業扱い
「見るだけ」「拭くだけ」「写真だけ」で近接限界を突破。
対策:単独禁止を原則に、やむなし時は電話復唱+動画記録で“擬似二名体制”。
離隔・姿勢の設計不足
離隔は静止寸法ではなく、揺れ・反発・旋回の動的余裕まで含めて設計。
対策:可動域スケッチ、監視員の専任、指差呼称の定着。
第1の関門(計画段階):停電計画・切替手順・連系条件の文章化。
第2の関門(現地到着):KY(危険予知)シートで**“今日の要注意3つ”**を書き出す。
第3の関門(作業直前):直前検電・短絡接地と養生。
第4の関門(作業中):指差呼称と立入監視、変化(風・人・工程)発生時の中断宣言。
第5の関門(復旧):復旧チェックリストの読み上げと署名。
いずれも5分~10分でできる行為で、**“中断する勇気”**が最後の砦になります。
共通(全作業)
今日触れる可能性がある充電部を3つ書いたか
停電→施錠・表示→直前検電→短絡接地を声出しで確認したか
単独作業なし(やむなし時は電話復唱+動画)
立入区分はテープorバーで目に見える形にしたか
送配電線路・伐採・建柱
最小離隔(mm)と可動域をスケッチ化
監視員の氏名と立ち位置を決めたか
風・傾斜・反発の再評価タイミングを決めたか
受配電設備(通線・点検・撤去)
露出充電部の養生とラベルを確認
図面の版数を復唱(v●●)
復旧時の切替順を読み上げ→署名
屋内配線・照明
相序・極性をテスターで実測→ラベル
プラグ切離しは無電後に写真記録
漏電遮断器の試験ボタンを押した記録
「直前検電しました、OKです」→「復唱:直前検電OK」
「旋回します。停止よし、離隔よし、周囲よし、旋回」
「変更あり。作業中断、KYを更新します」
「復旧読み上げ開始。主遮断器OFF、連系遮断器OFF…」
現場の言葉は短く、肯定形で、誰が言ったか分かる声量に統一しましょう。
一枚図(最新版):受電点~分岐~現場、危険部位は赤、無電予定は青。右上に版数と日付。
当日差分シート:変更点のみを赤入れで追記。
手順ショート版:停電→施錠・表示→直前検電→短絡接地→養生→作業→復旧。
復唱カード:主要チェック項目に□を付けて読み上げ式に。
記録テンプレ:写真(盤内、養生、検電、復旧)→ファイル名の型を固定。
教育:月1回、10分間の“盤内KYミニ研修”(写真1枚から危険3つを言語化)
評価:
直前検電の写真記録率(目標90%以上)
単独作業率(ゼロを目標に)
中断宣言件数(“多い”ことを称賛する)
版ズレ指摘件数(“見つけた人”を表彰)
Q. 軽微な点検でも停電は必要?
A. 活線部に近接する可能性が1%でもあるなら必要です。最低でも直前検電と養生は外せません。
Q. 二次請け以降にも全部配るべき?
A. 配らない前提で計画しないこと。版数と当日差分まで含めて配付し、配布リストに記名を。
Q. 雨天で仮設を使い回すのは?
A. IP等級・漏電遮断器感度を満たさない仮設は使用禁止。“一時凌ぎ”ほど事故率が跳ねます。
事故は受配電設備内の活線近接、送配電線路の離隔不足、屋内配線の逆接に集中。
根本は情報共有の断絶と直前検電の欠落、単独・軽視。
5分点検カードと復唱、写真記録が最もコスパの高い対策です。
現場は今日も動いています。**“中断する勇気”**をチームの文化にしましょう。
——私たちは、誰一人、感電で失わない現場を目指します。
――職人の空間に、緑の呼吸を。
KOI-DENの事務所に足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのは天井から吊るされた緑のオブジェたち。
板付けされたビカクシダ、苔玉、そして無骨な木の棚の上に並ぶ多肉植物や塊根植物たち。
どれも電気工事の現場とは対照的な“静かな生命力”を放っています。

和名:コウモリラン(蝙蝠蘭)
学名:Platycerium spp.
原産地:東南アジア、アフリカ、オーストラリアなど
分類:ウラボシ科ビカクシダ属(シダ植物)

ビカクシダは樹木に着生して生きるシダ植物。
葉には、根元を覆う「貯水葉」と、ツノのように伸びる「胞子葉」の2種類があります。
この独特な形が「コウモリの羽」に似ていることから“コウモリラン”という名が付きました。
KOI-DEN事務所では板付けと苔玉の2パターンで管理され、日光と風をうまく取り入れた配置が特徴的。
作業場に自然なリズムと清涼感をもたらしています。
学名:Agave spp.
原産地:メキシコを中心とした乾燥地帯
分類:リュウゼツラン科アガベ属

多肉植物の中でも特に人気の高いアガベ。
葉先に鋭いトゲを持ち、光沢ある葉が放射状に広がる姿はまるで“金属の彫刻”。
乾燥に強く、強い日差しを好むため、日当たりの良い窓際でKOI-DENの事務所に力強い印象を添えています。
“忍耐と再生”の象徴ともいわれ、職人の粘り強さを思わせる存在です。
学名:Pachypodium spp.
和名:象の木/キリンの木
原産地:マダガスカル・アフリカ南部

幹が太く、水をたっぷりと蓄えるパキポディウムは“乾燥に生きる知恵の象徴”。
トゲに覆われた太い幹から可愛らしい葉を伸ばす姿は、荒野の中のオアシスのようです。
KOI-DENのデスク上では、LEDライトの下で堂々と立ち、根気強く育つその姿が、日々の作業への粘り強さを映しています。
学名:Ficus pumila
分類:クワ科フィカス属
原産地:東南アジア

小さなハート形の葉をつけるツル性植物。
白い斑入りの品種は、明るい場所でより色彩が映えます。
KOI-DENの事務所では、無骨な木材や金属の棚に柔らかさを添える役割を果たしており、空間に“癒し”と“彩り”を加えています。
風が吹くたびに小さく揺れる葉が、まるで呼吸をするように静かな時間を刻んでいます。
分類:サボテン科(Cactaceae)
原産地:アメリカ大陸の乾燥地帯

水分を茎に蓄え、ほとんどの葉をトゲに変えた“乾きの王”。
KOI-DENの事務所では、光を反射して輝く姿が印象的です。
見た目の無骨さとは裏腹に、非常に強く生命力に溢れた植物であり、
“少ない条件でも生き抜く強さ”を象徴する存在として職人たちの空間にぴったりです。
KOI-DENの事務所にある植物たちは、ただのインテリアではありません。
電気工事という「光」を扱う仕事のそばで、自然の光と呼吸を感じさせる存在。
それぞれが持つ生命力と造形美が、現場の緊張感を和らげ、働く人の心に“余白”を与えています。
これらの植物たちは、KOI-DENのもう一つの職人魂――
**「丁寧に、誠実に」**という理念を、静かに語っているのかもしれません。