-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年2月 日 月 火 水 木 金 土 « 1月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

こんにちは。練馬区桜台の電気工事会社「株式会社コイデン」です。
「日本の発電所といえば?」と聞かれたら、多くの人が思い浮かべるのが 黒部ダム ではないでしょうか。富山県にあるこの巨大ダムは、観光地としても人気ですが、実は日本の電気を支えるうえで欠かせない存在です。
今回は電気工事士の視点から、黒部ダムの「凄さ」を解説します。
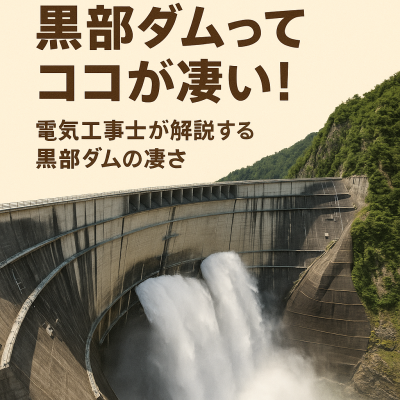
目次
正式名称:黒部ダム(黒四ダム)
所在地:富山県立山町
完成:1963年
高さ:186m(日本一のアーチ式ダム)
長さ:492m
総貯水量:約2億立方メートル
発電方式:水力発電(黒部川第四発電所ほか)
高さ186mというスケールは、東京の高層ビルと比べても圧倒的。
特に「アーチ式」と呼ばれる構造は、水圧を両側の岩盤に逃がす仕組みで、膨大な水を効率的に支えるための最先端技術でした。
電気工事士目線で見ると、この高さに合わせた送電線や発電機設備の設計・施工は、今でも大規模工事の教科書のような存在です。
黒部ダムからの水は 黒部川第四発電所 に送られ、最大33.5万kWを発電します。
一般家庭の使用電力(1世帯あたり平均400〜500kWh/月)に換算すると…
約8万世帯分の電力をまかなえる規模。
しかも水力発電は「二酸化炭素を出さないクリーンエネルギー」。黒部ダムは環境面でも非常に価値の高い発電所なのです。
黒部ダムのもう一つの凄さは、建設工事そのものです。
掘削したトンネル延長:約80km
搬入資材の総量:約1,000万トン
殉職者数:171名
当時は機械化も不十分で、資材運搬やトンネル工事は極めて過酷でした。
特に「破砕帯(はさいたい)」と呼ばれる大量の地下水が噴き出す難所の突破は、日本の土木史に残るエピソードです。
電気工事士として現場を想像すると、仮設電源や照明の確保、資材運搬用の電動設備など、当時の工夫がどれほど大変だったか計り知れません。
黒部ダムは「発電所」でありながら、年間100万人以上が訪れる観光名所でもあります。
夏の放水観光(観光放水)では、1秒間に10トン以上の水が放出され、迫力満点。
周囲には立山黒部アルペンルートがあり、観光と電源開発が共存している珍しい例です。
ダムの役割を理解することで「ただの観光地」ではなく、日本の電力を支えるインフラとしての価値も見えてきます。
黒部ダムから学べることは、電気工事士の仕事にも直結しています。
電気設備は規模が違っても原理は同じ
発電所の大型タービンも、家庭用のモーターも「電気を効率よく使う」点では共通。
現場の安全が最優先
黒部ダム建設で多くの犠牲が出た歴史は、今の安全基準をつくる原点でもあります。
インフラの裏にある努力を知ると電気の価値が変わる
普段スイッチ一つで使える電気のありがたさが、黒部ダムを知ると実感できます。
黒部ダムの凄さは単なる大きさだけではありません。
日本一のアーチ式ダムという規模
8万世帯分を支える巨大な発電力
世紀の難工事と呼ばれた建設史
観光と電源開発の両立
これらすべてが重なって「黒部ダムの凄さ」を形づくっています。
電気工事士として言えるのは、黒部ダムは「電気の大切さを教えてくれる生きた教材」だということです。